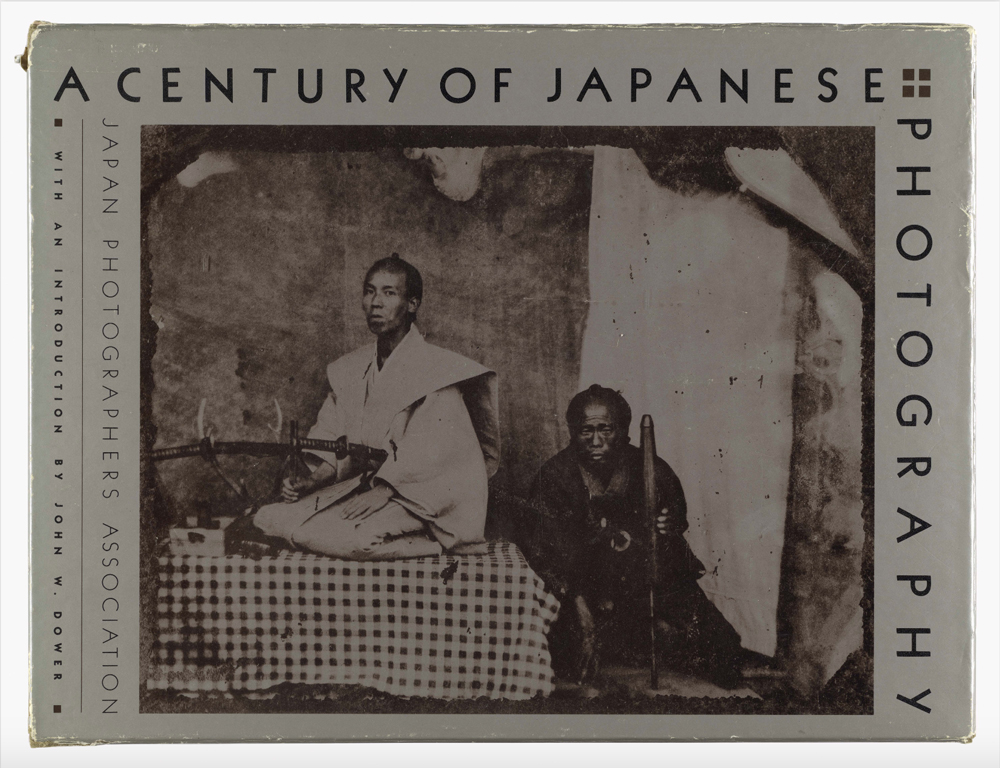
- 原文
- 英語 (略称)
- 出版形態
- 記事
- 出版
- 1980年
このファイルは英語が原文で、ダウンロード可能です。
日本語訳は以下に表示。
見るための手だて、記憶するための手だてー戦前日本の写真
ジョン・W・ダワー
写真家は現実を映すとともにそれを創造し、今という時の断片を捉えながら過去を創案する。彼らのこの貢献が大きなものであることは言うまでもないが、それは同時に不透明性を孕んだ貢献でもある。初期の写真家たちは<photograph>、つまり日本語で文字通り<真実の複写>、<現実の複製>を意味する<寫眞>という二つの表意文字が巧みに表したことをなし遂げようとしたのだが、写真家による貢献は、実際にはそれよりも明らかに曖昧なものだったのである。
この二文字の表現が定着したのは、写真が西洋からもたらされたおよそ20年後の1860年代半ばのことだろう。日本で初めて写真が撮影された日付は1841年6月1日とされており、これはルイ・ジャック・マンデ・ダゲールとウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットが同時期に生み出した発明をそれぞれパリとロンドンで公式に発表した僅か2年後のことであった。この日付を1841年だとする逸話は虚偽だとされているが、1853〜1854年にマシュー・ペリー提督が実施した砲艦外交に先立ち、長崎のオランダ人によって写真が封建時代の日本にもたらされたことは間違いのない事実である。1840年代後期に書かれたいくつかの日本の文献は、ダゲレオタイプ(オリバー・ウェンデル・ホームズはこれを<記憶を宿した鏡>と呼んでいた)を<印象を刻み込む鏡>あるいは<反射像を刻み込む鏡>(印象鏡/印影鏡)と表現しており、少なくとも1848年までには日本の<蘭学>学者たちがこの写真術の習得に励み、不確実ではありながらもそれなりの成果を得ていたと記している。現存する日本最古のダゲレオタイプは、ペリー提督率いる遠征隊の一員が1854年に撮影したものである。現存する中で日本人写真家の手によるとされる唯一のダゲレオタイプは1857年に撮影された大名・島津斉彬の肖像だが、これは1975年に初めて発見された。<瞬間的な>湿板法(1851年にイギリスで発明され、その後すぐにダゲレオタイプとタルボタイプに取って代わった手法)の導入と、日本最初のプロ写真家で、1862年にそれぞれ写真スタジオを設立した上野彦馬と下岡蓮杖の登場により、日本の写真は1850年代後半に本格的に花開く。
西洋がダゲレオタイプとタルボタイプという初期写真術により膨大な写真アーカイブをもたらしたのに対し、日本の写真の遺産は僅かなものだったが、写真が日本に導入されたタイミングは、日本を研究する者たちにとって特別な奥深さを持つ。その導入の時期は、日本が封建社会から資本社会へと移行を遂げるきっかけとなった1868年の明治維新よりも10年以上も前のことであった。封建制度の下で生きた人々の顔や7世紀にわたり国を支配した武士階級の最後の時代を、カメラは捉えていた。こうして早く日本に行き着いた西の独創力の小さな所産は、その後次々と到来する西洋の文化や技術により変容していく日本を記録していく。日本に到達した直後から、カメラは近代日本国家が辿った劇的な道のりの目撃者となった。目覚ましい技術革新、後進性と利己主義が根強く存在する中での世界主義、産業化、ブルジョワ文化の台頭、一連の帝国主義戦争、果てには1945年の惨状までをも記録したのである。
西洋において、写真史家は日本を軽視し、近代日本史家は写真のみならず、絵画、ポスター、版画、風刺画など、日本のあらゆる視覚的記録をなおざりにしてきた。本巻に掲載されている写真が物語るように、1945年以前に日本人が撮影した写真は実に多様で示唆に富むものであり、それらが写真の分野にもたらした貢献は絶大なものである。歴史の証人という意味では、歴史学者の多くが頼ってきた従来の文献を補い、時には正す、頼もしい補足的材料となる。また、歴史学者であるなら注意深く扱うべき、人の目を欺くような性質を秘めた証人でもある。
こうした用心が必要な理由を、ここで簡潔に述べておこう。カメラは、筆記者が記録し得ないこと、より端的に言えば、文字では表現できないことを伝える能力を備えている —つまり、微細な部分、感覚的なもの、そして言葉の範疇を超えた世界を表出することができる。カメラは、時に見過ごされ、時に意図したのとは違った形で記憶されてしまう物事を記憶する鏡なのである。しかしカメラは、過去を記録する装置としては歪んだ鏡にもなり得る。ここで明らかに言えるのは、カメラが記憶することとは写真家が意図的に選んだものであり、手腕のある写真家であれば、それが秩序であれ混乱であれ、陽光であれ影であれ、特異性であれ普遍的な人間性であれ、得てして自分の撮りたいものを見出すということだ。より不透明な視点から言うならば、写真はそれがたまたま捉えたイメージや出来事に、ある種の無作為な永遠性を授けることができる。そして、物事を記憶するために非常に理にかなっていて説得力のある方法と思われたものは、同時に物事を忘れる方法にもなり得る。つまり、後の時代を生きる者が写真を目の前にしたとき、何らかの理由でそこに写されなかった、または記憶に残るような形で写されなかった事柄を、その写真の中に見てとることは文字通り不可能なのだ。写真の中に閉じ込められた瞬間は、止まることなく流れ交わり続ける歴史の本質とは相反するものである。そして、カメラは被写体のポーズに過ぎなかったものをその者の人格へ、断片を全体へ、一過性を永続性へ、一瞬一瞬の時を永遠へと変えてしまうことで — または、型どおりのありふれた経験や辛く惨めで悲痛な体験に現実離れした古色を加えることで — 過去に深刻なダメージを与えることもできるのである。スーザン・ソンタグが実に説得力のある議論をした通り、カメラは平凡なものを美化するだけでなく、非凡なものを平凡化することもできる。つまり、カメラは残虐行為に対して人を鈍感にし、それに慣れさせてしまうことができるのだが、近代日本はこの情況に大いに貢献したと言える。カメラが人の知覚を均等化してしまうというこの行為は、それが写し出すさまざまな事象が実際には平等・同等でないことを考えれば、錯覚的であり、不道徳的ですらある。
こうしたことを踏まえても、やはり写真は我々が見るため、記憶にとどめるためになくてはならない、パワフルで遍在的な手だてであり続ける。時代が進み、印刷物が急速に普及するにつれ、歴史愛好家はより一層独自のやり方で自由に古い写真を用い、それに新たな意味を持たせるようになっていく。その一つとして写真の並列があるが、この手法がいかに複数の違ったレベルで機能するかを説明するには、1945年以前の日本の写真がよい材料となるだろう。一枚の写真の横にもう一枚の写真を並べることにより、単なる経時的な変化だけでなく、社会的な矛盾や歴史的な皮肉をも視覚的に表現することができる。侍の身なりをした若い男性一門の肖像写真と彼らの子孫が野球のユニフォームを着て写るグループ写真、ネクタイを締めた資本家たちと機械に囲まれた労働者たち、クラッカーや乾物、ビールなどを売りつける若く健やかな女性たちと海の向こうで人を殺し焼け死んでいく彼女らと同世代の男たち。19世紀の重苦しい白黒写真のすぐ隣に、世紀の変わり目まで廃れることのなかった色彩豊かな<錦絵>を置いてみることもできる。また、帝国日本が生んだ説教や巧言の横に、その内容を覆すような写真を据えることもできる。ストライキ、暴動、デモの写真に添えられるのは、日本における社会的な繋がりが本来備えている<調和>を謳った説明文。炭鉱作業員、貧しい小作人、貧民街の住人などの写真に付与されるのは、古くから伝わる日本の<美風>を賛美する引用文の数々。国外で繰り広げられる武力侵略や残虐行為を撮った写真に付けられるのは、<共存と共栄>に関するキャプション。これと同時に、メーデーのデモ行進で最前列に立つ女性労働者の姿を捉えた写真や、軍国主義の高まりにつれ超現実主義者の影響が色濃くなっていく様を見たとき、西洋人の多くが戦前の日本に対して持っていた固定概念が崩れ去るかもしれない。
日本に伝わった写真は、西洋諸国が科学的かつ美学的なものの見方に与えた大きな影響の一部をなすものであった。当初、写真の探求にはお金がかかり、撮影に必要な基本資材を輸入する際には特に費用が嵩んだ。洋学のさまざまな分野に携わり、写真技術研究の最初の後援者となったのは、その頃国の土地を何百にも分割していた領土のうちのいくつかを司る大名たちであった。九州の薩摩藩が先導した当研究を、水戸、筑前、福井、天童、松前、土佐の各藩の大名も擁護した。1850年代に日本が開国すると、写真家を目指す日本人は多くの外国人から直接指導を受けるようになる。強まる一方であった西洋の影響が他のどこよりも顕著に表れていたのは、外国との三つの接点であった長崎、横浜、函館だった。長崎と横浜は指定の<条約港>として1858年に外国人と対外貿易に向けて開港し、函館はそれに先立ち1854年に開港した。こうして、九州、関東地方、北海道の三つの地域は、日本の初期の写真の拠点となった。これは、帝国主義者の要求に沿って用立てられた地理的状況と大まかな一致を見せている。
知覚的・美学的<リアリズム>を表現する新様式として、写真は日本人が西洋の絵画や版画の中に見出した影の描写や遠近法への認識を強め、大和絵、墨絵、版画、いかがわしさを孕んだ浮世絵など、日本固有の伝統的な視覚的表現が明らかに欠いていた、描かれる主題への忠実性をもたらした。人間が主題となったとき、カメラが記録した顔は、日本の肖像画に描かれる極めて様式化されたそれとは大きく異なっていた。しかしながら、物質界を認識・描写する上で、より<現実的な>方法として写真の貢献を語ることは、当惑、そして危険すらも伴う。1500年代中期に始まったいわゆる<キリスト教徒の世紀>に日本人はすでに西洋のものの見方に接触していたが、いくつかの注目すべき例外を除いて、彼らは意図的にそれらの方法に背を向けた。カメラ・オブスクラは17世紀に西方から中国へ、1718年に中国から日本へと伝わった。18世紀半ばに版画家・円山応挙が用いたこの手法を、その後、洋風画を描いた絵師・司馬江漢も採用している。1730年代、奥村政信はヨーロッパ芸術の遠近法を用いた<浮絵>を実験的に制作し、その数十年後には円山応挙が浮世絵の一種である<眼鏡絵>で絶大な人気を得た。さらに特筆すべきは、日本の美学的伝統には事実に即した緻密な様式も含まれていたことである。例えば、古くから伝わる仏教彫刻には力強く写実的な傾向が見られ、その後の封建時代には、生粋の自然主義者への手引きとしても十分なほどの詳細さと正確さを持つ動植物の色付きの描写が全盛を極めた。そして、現実の複製を可能にした新しい機械に言語的・概念的に先立つものとして挙げられるのは、中国の明朝・清朝から長崎を通じて日本に渡った<写生画>、 すなわち生命を複写する絵画の流派であった。このように、写真は日本人に外界を様式的・印象的に描かぬよう説いたのではなく、むしろそう描くよう奨励したと言えるだろう。
実のところ、より興味深いのは次のような問いではないだろうか—もし伝統芸術が日本の初期の写真に貢献したとしたら、それは一体どんなものだったのか?西洋においては、初期の風景写真や建築写真の構図に、版画の影響を見てとることができるであろう(そして後には、逆に写真が版画に影響を与えた)。また、西洋絵画の偉大な伝統が写真にインスピレーションを与えたことは、1840年代にデイヴィッド・オクタヴィウス・ヒルとロバート・アダムソンが撮影した著名なタルボタイプの肖像シリーズを見れば明らかである。一方、日本の写真家の目は木版画特有のダイナミックな構図と線に、さらには墨絵の古き伝統が誇る統制の取れた形や余白の使い方に影響を受けているはずだと思われがちである。実際、墨絵は白と黒の美学を長きにわたり牽引してきた素晴らしい画法と言えるであろう。しかし実際のところ、黎明期の日本人写真家は、これらの伝統的なものの見方には影響されていなかったようなのである。19世紀の日本の写真は多くの点で長けているものの、特徴的な構図と線、特筆すべき空間の使い方などは見受けられないのである。世紀の変わり目に<芸術写真>の流行が訪れて初めて、日本の写真家は絵画からインスピレーションを受けるようになったが、この時でさえ、彼らは日本の伝統芸術ではなく、同時代の西洋画からひらめきを得ていたのだ。
もう少し分かりやすい例を挙げると、黎明期の日本の写真は、名所の光景、喚情的な女性の描写、役者の肖像画、職人や労働階級の似顔絵など、封建時代後期の郷土芸術によって既に世に広まっていた主題のいくつかを取り入れた。しかし、こうした主題の表現に影響を与えたのは、カメラの持つ技術だけではなく、条約港で盛り上がりを見せた観光事業と西洋人の嗜好であった。外国人の美的センスはあらかた平凡なものだったが、その一方で彼らは旺盛な好奇心と財力の持ち主でもあった。これが、今なお存在する19世紀半ばの日本の詳細な記録が写真によって残された主な要因なのである。写真の購買者であり写真家でもあった西洋人は、日本人の写真家が見過ごしてしまったであろう事柄に興味を抱いた。日本人にとっては当たり前の慣習も、外国人の目には魅惑的に映ったためである。さらに外国人は、普通であればカメラの前でポーズを取ることなどまずなかった職種や下層階級の人々を包括的に写真に記録することに関心を寄せた。種々の職人や庶民の姿は、12世紀に絵巻物が多く制作されるようになってから風俗画の世界で絶えず描かれてきたが、19世紀半ばという時代において写真機材は非常に高価であったこと、また肖像写真を撮影してもらう費用が比較的高くついたことを考えると、日本庶民の肖像に強い関心を示した西洋市場の存在なくして、これらの貧しい人々が被写体となることはなかったであろう。
こうした状況から生まれた結果の一つは、1850年代から明治時代にかけて撮られた日本と日本人の写真のうち特に興味深いものの多くが外国人によって撮影されたか、少なくとも外国人の手に渡ったということである。日本を離れ、現在は西洋のアーカイブや希少本に保存されているそれらの写真は、権力の座にあった武士階級の男たち、女たち、子供たちだけでなく、種々雑多な人々—遊女、人力車の引き手、駕籠者(かごのもの)、工匠、小売店主、行商人、農民、医者と患者、住職、寺子屋の児童、橋の下の孤児 — を捉えている。この一連の写真がとても印象的なのは、カメラの前でポーズを取った被写体が誰一人として名前を残さなかった故であろう。
ありとあらゆる種類の人々を捉えた写真一式は、写真で辿る従来の日本史とはまた別の歴史を語り得るものである。すべてを網羅しているわけではないものの、本巻掲載の写真の何枚かを見ることで、その一味違った日本史の片鱗を伺うことができるだろう。日本人は在留外国人や一時的に滞在した水夫など、条約港を賑わせていた人々の肖像写真を撮影し(要望があれば和装を着せ、時には日本人の若い女性とともに)、日本での思い出の品となるような写真を販売することで、外国人の需要に応えた。このような商売は、関東地方の横浜・東京を拠点として活発に行われた。下岡蓮杖が1868年に横浜で二階建ての店舗を開店した際には富士山を模った巨大な看板が掲げられ、その神聖なる山の左右を飾ったのは英単語<Photographer>であった。<Renjio’s Branch House>(名前には旧式のローマ字綴りが使われた)という英文字がその下を這うように書かれ、それとは別の大きな看板には<Pictures Up Stairs(写真は上階へ)>と謳われていた。外国人客を想定した写真には英語の説明書きが添えられ、その一方で、これと言って特徴のない風景写真付きの葉書も売られた。中には明らかに俗受けを狙った写真もあった。劇作家の二人組・ギルバート&サリヴァンが子供を売る場面(籠の中の可愛い赤ん坊の歌を今にも歌い出しそうな様子)、赤い血を流し緑がかった顔をした武士が、その場面にふさわしい色合いを帯びた写真の中で<腹切り>を演じる様子、<マカロニを食べているところ>、<寝室の娘たち>、<家での入浴の場面>、等々。こうした観光客向けの写真制作は20世紀にも引き継がれ、明治時代に英語で出版された書籍の多くに図版を提供した多作の写真家・小川一眞が、その代表格であった。
条約港で生み出された初期の写真の多くは、無名の写真家が同じく身元不詳の人々を撮影したものだったが、その中には横浜と長崎で娼婦や<茶屋の給仕>として働いていた女性たちが全裸や半裸でさまざまなポーズを取ったものも含まれていた。中でも、本巻には掲載していない最も品位に欠ける写真からは、芸術を気取るようなてらいは微塵も感じられない。被写体のポーズは硬く、陰毛の部分にぼかしが入れられているものの、股間が遠慮がちに隠されるようなことはなく、露出されているケースがほとんどである。このような写真の主な顧客もまた外国人であり、この点において初期のヌード写真は、条約港において売春宿が営まれていたという側面、そして帝国主義には付きものの性的搾取が行われていたという当時の状況を忍ばせる。それと同時に、日本の伝統芸術そのものが、遊女、小間使い、乱れた身なりの下級芸者などを描いた木版画から<春画>の溢れんばかりの性描写に至るまで、あからさまなエロティシズムを得意分野としていた。卑猥さ、絵などによる刺激的な表現、そして性的な搾取は、輸入されずともすでに日本に存在し、一糸纏わぬ姿の描写は、それが西洋のように高尚な芸術へと高められることはなかったものの、決してタブーではなかったのである。
このように、初期に撮られたヌードやセミヌードの写真は、条約港の住人たちの嗜好を満たす術の一つであったと解釈できるが、これはむしろ予想通りの展開だったと言える。つまり、日本文化に根差す色情の伝統から、哀れな娘たちが(そして、この頃西洋のトランプに描かれたエロティックな女性像の哀れな妹たちが)生まれたという流れがあったのだ。前述の入浴の写真に代表されるような構図は芸術風を吹かしているように見え、同時に純朴さのようなものも感じさせるが、さほど刺激の強くないこの初期の性的描写を目にした時に全体の印象として残るのは、それが実際に<現実を転写した>イメージだということである。しかし、ここに切り取られた現実は、撮影した写真家が意図していたイメージや、被写体となった女性たちの実際の経験とはまた違う現実であった。確かに、この写真に転写された現実は、歓楽街で描かれた春画や浮世絵の淫らで滑稽ですらある性表現とは天と地ほども懸け離れたものだ。宿場町の娼婦が無表情に化粧をする様子などを写した写真は、リアリズムを追求する意図なくして現実味のある場面を効果的に捉えた好例である。より下品なポーズを取って写るモデルたちは皆、幼く、その表情は硬く虚ろで、肉体的に決して魅力的でない者もいる。彼女たちは明らかに、その場面への参加者ではなく、性的な対象物である。現代の日本人評論家が見れば、そのずんぐりとした身体、少し曲がった背中、全体的な顔の特徴などはどれも性的な印象など与えず、多くの子女が条約港や都心へと雇われていった東北地方などの貧困地域で惨めに暮らしていた農村の人々を思い起こさせることだろう。1890年代後半から、絵画、彫刻、写真に登場した裸体の描写を政府が厳しく規制するようになると、展示作品のうち関係当局が道義に反すると判断した箇所を布製の<アンダースカート>で覆い隠すという例も見られるようになる。こうした規制は1918年まで緩むことがなく、本格的なヌード写真が日本で撮られるようになったのは1920年代に入ってからであった。
日本の写真黎明期に条約港で出回ったヌード写真から一転して、世に知られる美女たちの肖像を上品に撮ったピンナップ写真という息の長いジャンルが生まれた。これらの写真は、有名な芸者たちを描いた気品溢れる木版画の系譜を継ぐものである。カメラが捉えた明治の美女たちのほとんどは、やはり芸者だった。哀れで名前すら分からない子女のヌードとは対照的に、芸者たちの多くはすでに名声をものにしており、そうでない者も撮影後すぐに世間に知られるようになる。モデルが美人であるかだけが実質的な問題であり、また、春信、歌麿、国貞などの木版画の巨匠たちが賛美してきた顔立ちを少し柔らかくしたものが美の基準とされた。瓜実顔、色白の肌、鼻筋の通った高い鼻、官能的な口元、アーモンド型の目、そしてかなり太めの眉毛が理想とされた。ピンナップ写真に収められたこれらの申し分のない均整の取れた顔つきからは、物腰、知性、趣といったものが滲み出ている。中には当世風の西洋のドレスを纏っている芸者もいるが、ほとんどは着物姿で写っている。
1870年代に入り、鶏卵紙の登場により複製が容易になると、こうした美女たちの姿や、伝統的な木版画の主題として頻繁に描かれてきた俳優や名所のイメージを厚い紙に貼り付けたものが、専門店で木版画と同じように売られるようになる。日露戦争(1904〜1905年)が始まる頃には印刷工程が一層高度化し、美女が印刷された標準サイズの葉書が日本中どこでも手に入るようになり、表向きのプロパガンダでは天皇のみに意識を集中させているはずの下士官兵たちは、こうした葉書を前線へと携行した。その後、舞台女優と映画女優が人気芸者と同一視されるようになり、それまでと同様に顔立ちに重きを置いた美ではあったものの、より<エキゾチックな>美の理想(つまり、西洋化された理想)が<ブロマイド>と呼ばれたピンナップ写真の形で国中に浸透していく。極めて理想化された女性美の分野において、日本人は1945年よりも後の時代まで<顔から解放される>ことはなかったと言われている。
俗受けを狙った土産用の写真が流布し、初期の写真作品の多くに特徴的な外国人や大衆に迎合する傾向が強まる中、とりわけ関東地方において、日本の写真の先駆者たちはより抑制された表現を目指すようになる。そうした新たな表現の一つで、他国と同様に日本でも主流となったのが肖像写真である。まず初めに、これもまた他国でも起こったことなのだが、カメラは神秘的な力を持つという様々な迷信が生まれた。その一つは「一度写真に撮られると、あなたの影は消えていく、二度撮られれば、あなたの命は縮まってしまう」という盲信で、他にも、三人が同時に写真に撮られると真ん中の者が早死にするという説などが出てきた。電信を始めとする西洋の技術に対して人々が抱いた恐怖と同様に、写真への恐怖心もすぐに一掃され、お金を何とか工面できた日本人は写真家のスタジオに押し寄せるようになる。中でも真っ先に写真に飛びついたのは侍だった。下岡蓮杖は「血気にはやる各領土の武士たちは、せめてこの空蝉の世に生ける印を、何かの形に留めたいとの念願から写真を写して置こうと考えた」と語っている。こうして、人々は自分の影を失うことを恐れる代わりに、それを後世まで残したいと願うようになったのである。
1868年に旧体制が覆されるよりも前から侍が最後の無益な抵抗を見せた1877年に至るまで、武士たちはカメラの前に座り続けた。一人で写る者もいれば、同士、家臣、家族、遊女らと一緒に写る者もいた。刀二本を携帯する伝統的な二本差し姿だけでなく拳銃を手に撮影することもあり、そのポーズはゆったりとしたものから硬いものまで幅広く、目線もまた、真っ直ぐカメラを見据えたり脇に逸らしたりと様々である。彼らが示したのは、侍としての地位、自尊心、そして予測不可能で爆発的とも言える資質であった。特に若い青年の肖像写真は、日本の<近代化>への立役者となった、若々しく急進的で揺るぎない、それでいて曖昧さも兼ね備えた彼らの人格的エネルギーを効果的に伝える<形見>となった。1868年の旧封建制転覆よりも前に撮られた写真には、策略の成就を待たずして散っていった倒幕派の有名な<志士>たちの肖像や、彼らのうち生き延びた共謀者たちがフロック・コートを纏い、新制度の中心人物として再び撮影された肖像がある。この後者の姿、つまり新体制の第一人者として写った姿が、生き残った者たちが好んだイメージであり、後世の人々の記憶に残った肖像なのだ。
19世紀半ばの日本における肖像写真の巨匠・上野彦馬は、1862年、若干25歳で長崎に写真スタジオを開く。1868年以前、上野は明治維新の大義のために戦った活動家を有名・無名に関わりなく主題とし、また条約港に住んでいた侍以外の者や外国人など、ありとあらゆる人たちをカメラに収めた。上野や彼と同時代の写真家たちが手がけた未修正の肖像写真に見られるくっきりとした照明の光と装飾性を欠く設定から、彼らが芸術性の高いソフトフォーカスの撮影技術が到来するよりも前の世代であったことが分かるが、そうした手付かずのクオリティはおそらく、満ち足りた今の時代の人々の心を惹きつけることだろう。感傷的なムードや写真家としての技巧の欠落こそが、苦しい時代を生きた者たちの<真実>をより切実に表現していると言えるからである。
このように、写真は幸先の良いスタートを切ったにもかかわらず — そして、上流階級が描かせてきた肖像画の伝統、個人の歴史を作ろうとする傾向、日本の写真コレクションの<決定版>たるものを編集しようという異常なまでのこだわり、明治時代の指導者の絶大なる自尊心など、条件はすべて揃っていたにもかかわらず — 意外にも日本の写真家は、著名な同胞たちを一貫性のある体系的な方法で写真に残そうとはしなかった。上野と下岡の時代から日本で撮られてきた個人の肖像写真、家族写真、集団写真の数は、おそらく世界中のどの国にも匹敵するか、それを上回るほど膨大であろう。しかしながら、日本にはマシュー・ブレイディが制作した『著名アメリカ人のギャラリー(The Gallery of Illustrious Americans)』(1850年)や複数巻からなるフランスの『現代ギャラリー(Galerie contemporaine)』(1876〜1884年)に比肩するものは存在しない。日本人の中に、フランスのナダール(本名:ガスパール=フェリックス・トゥールナション)、英国の女性写真家ジュリア・マーガレット・キャメロン、スコットランドのヒルやアダムソンのような19世紀肖像写真の巨匠と呼べる写真家はいなかったのだ。
もっと広い視点で見るなら、記録写真と一般に呼ばれる写真の日本における発展は、それなりの時間を要したと言えるであろう。写真活動をスタジオの中だけに制限しなかった上野彦馬は、屋外での写真撮影にも際立った才能を発揮する。長崎の入り江をパノラマで写した写真が条約港の物理的な風景を巧みに捉えているのに対し、人力車に乗った白人男性と、その後ろで彼の荷物を運ぶ雄牛の延々と続く行列を写した有名な一枚は、条約港の心理的な風景を効果的に描き出していると言える。上野は長崎近郊の丘をえぐり取って作られた巨大で醜い高島炭鉱などにもカメラを向け、さらには19世紀半ばの日本の戦争写真で最もよく知られる作品を残した。鹿児島の人気のない狭間胸壁を撮った1877年の写真は、芭蕉が俳句に詠んでもおかしくないような趣をたたえ、アメリカ南北戦争時代のしんと静まり返った戦場のイメージにも匹敵する一枚である。
しかし、この写真が持つより大きな意義は、その時代に戦争の様子を収めた写真が事実上他に存在しなかったことにある。日本には実用性に乏しいながらも十分と言える写真技術がすでにあったが、1868年の明治維新以前・以後とも、軍事闘争を掘り下げて撮影しようとした写真家は上野をおいて他にいない。ほぼ同時代に勃発したクリミア戦争とアメリカ南北戦争が実に詳細に記録されたことを考えると、日本の写真家が戦争の記録をし損じたという事実が殊に強調される。1877年、反動的な侍たちが新政府に対して7か月に及ぶ戦いをしかけた時ですら、日本で<ブレイディの兵士たち>に並ぶ写真を撮る者はいなかった。上野は実際、日本政府からこの謀反の様子を記録するよう委任され、8人の助手を引き連れて戦場に赴いた。ブレイディとその仲間が何千枚もの写真を撮影したのに対し、上野らの成果は69枚であった。このように、上野が記録した鹿児島の無人砦のイメージが素晴らしいのは、それが優れた写真だからというだけでなく、唯一無二の写真だからである。明治維新を軸に20年間続いた国内の対立と闘争の様子を知るには、昔ながらの木版画の手法で作られた<錦絵>の極めて大げさで信憑性を欠く描写に頼るよりほかない。日本において記録写真が揺るぎない位置を確保し本格的に発達したのは、世紀の変わり目に日清戦争が起こってからであったが、北海道の写真家たちから成る第三の先駆的グループによる写真作品には、ドキュメンタリー手法の起源とも言える力強いスタイルが見てとれる。
日本の写真の発展が、日本において最も発展の遅れていた北海道という地域で最高潮に達したという事実は一見意外なことのように思えるが、これは実のところそれほど驚くことではない。北海道はいわばアメリカ西部のような場所であり、不屈な入植者たちが次々と訪れた荒れた未開拓の領域だった。そして、失われつつあるアイヌ族の運命は、アメリカ先住民のそれと近似していた。北海道の初期の発展は外国人技術者たちの指導に依るところが大きく、彼らの多く(63人中46人)は、アメリカ政府の支援の下、同国のティモシー・オサリバンやアレクサンダー・ガードナーらが開拓時代の辺境の地で撮影した草分け的な写真に精通したアメリカ人であった。北海道における写真への関心は、地元大名・松前崇広の支援と函館在住のロシア人の指導により明治維新前から急速な高まりを見せた。北海道の最も偉大な二人のカメラマン・田本研造と木津幸吉はともに初期の頃はロシア人から写真術を学び、木津は1864年、北海道で初の写真スタジオを函館に開業する。しかし、この二人の写真師と彼らの同僚が最大の成果を上げた時期は、1871年—新政府が日本北部の島の発展を目指す開拓使10年計画を発表し、外国人の相談役を雇用し始めた年—に続く10年間である。この辺境の地の開拓に充当された総予算のうちの多くが写真制作に割り当てられ、その資金は、開墾と建設の進み具合を記録するためだけでなく、入植の見込みのある人たちに開拓事業の様子を宣伝するためにも使われた。1879〜1880年の2年間だけで、210,029円というかなりの金額が写真撮影の資材に充てられたのである。
北海道を拠点とした多くの写真家はそれぞれに名前が広く知られているが、関東地方の写真家たちと同様、彼らの写真のほとんどは個々の作品としてではなくグループ全体の貢献として伝えられてきた。武林盛一が撮った囚人の肖像写真などは明らかに特定の写真家によるものだとわかる作品であり、また初期の写真の大部分は田本の手によるものだとされているが、確かにそうであろう。しかし、ほとんどの写真は、その作者が誰なのか判明していない。アメリカ西部の芝土造りの小屋や開拓の町を切り取った写真と同じく、北海道で撮られた写真の大きな影響力は、忌々しい天候に晒された土地と粗末な建物に囲まれた厳しい生活の描写にこそある。中には、自分たちよりも背の高い木の切り株が並ぶ灰色の平原をうろつく男たちのイメージなど、超現実的とも言える印象を放つ写真もある。そして、このような写真の多くが開拓地を宣伝するために使われたという事実に、現代の人々は畏怖の念を深めずにはいられないだろう。秀作《樺太の猫》と同様、この写真が比較的遅い時期に撮られたという事実は、1870年代に入り開拓活動がより激化・組織化された後も、北部の厳しい環境がカメラを手にする者たちの際立った創造性を駆り立て続けたことの証しなのだ。
北海道(及び樺太)を住処とし、人種的・文化的に日本人と区別されてきたアイヌの人々を写し取った写真群は、一つのカテゴリーを形成する。1895年に制作された写真アルバムに鹿島清三郎が『The Ainu of Japan(日本のアイヌ)』と英題を付したことからも、これらの写真が外国人からの支持を得ていたことが伺える。アイヌ民族の研究資料のほとんどは、彼らの慣習的な活動を撮影用にお膳立てして捉えた写真や、アメリカ先住民の首長たちのポートレートを彷彿とさせるカメラを真正面から見据えた肖像写真であった(ただし、アイヌの人々と違い、アメリカ先住民の多くはその名前を記録されていた)。カメラがほんの束の間、被写体にこうしたお決まりのポーズを取らせる代わりに、物乞いのようなぼろ切れを着て地面に呆然と寝そべっているアイヌ人を捉えたときに初めて、絶滅寸前の危機に陥っていた民族の失意と屈辱が、忘れがたいイメージとして結晶化したのだと言える。
プロ写真家の第一世代は才能溢れる男性ばかりだったが、彼らは大変高くついた。1850年代から1860年代にかけて写真術を学んだ者たちは皆、英語とオランダ語、さらには西洋科学の基礎をも習得せねばならず、彼らの多くがその分野の達人として高く評価されるようになる。1872年の流行語<文明開化の七つ道具>には、新聞、郵便、ガス灯、蒸気機関、展覧会、飛行船に加え写真も含まれ、その一方で写真家たちは滑稽五行詩、歌、小説、劇などに登場し、後に彼ら自身の写真作品に取って代わられた<錦絵>にまで描かれた。1870年代に入る頃には、100人を超えるプロ写真家が日本の至るところで活動しており、その中の何人かはその10年間に出版された様々な<紳士録>に名を連ねた。彼らはもっぱら湿板法による撮影を行い、それに必要な機材や資材は、条約港の西洋人仲裁者を介して西洋から輸入されたものばかりであった。
しかし、写真の人気が高まるにつれ、写真家はそれほど高く評価されなくなってしまう。この変化を如実に示しているのは、真に優れた技術を備えたプロフェッショナルではなく、むしろ月並みな職人を連想させる言葉が、写真家を表す単語として選ばれたことである。開拓時代のカメラマンたちが<写真の名人>を意味する「写真師」として知られていた(今でも知られている)のに対し、彼らの継承者であり1880年代以降に商業的な写真を撮った写真家たちは、単にその撮影が行われた仕事場と結びつけて認識された。つまり、彼らは「写真屋」(文字通り<写真の部屋>)、または<写真店の人>を意味する「写真屋さん」と呼ばれたのである。言語と科学を駆使する代わりに、写真家はありとあらゆる小道具を集め、被写体の容姿だけでなく自らの写真の腕をもよく見せるため、背景に色付けを施した。こうした転換は、技術革新、特に1883年に初めて日本に導入され、写真をより簡単・迅速・安価なものにした乾板の登場と時を同じくした。今や、より幅広い身分の民衆たちが特別な機会に写真を撮ってもらうことができるようになり、その一方で、新たに出現した特権階級のアマチュア写真家は、本業として写真の道に進めるようになっていく。
浅沼商会と小西本店が率いる資本家たちはゆっくりと、しかし確実に国内製造と西洋の供給元からの直接輸入を活発化させていった。このことからも分かるように、写真を取り巻く前述の発展は、日本の産業革命と国内における企業家精神の多様化とは切っても切り離せないものであった。それと同時に、印刷技術の進歩が、書籍、雑誌、新聞など、より広範囲に及ぶ紙面への写真の普及を促した。1870年代の後半以降、写真は時折、印刷されたページに貼り付けた状態で出回った。そして、東京日日新聞が新たに発足した国会の議員たちの写真を折り込みに掲載した1890年が、日本のジャーナリズムにおける節目となった。しかし、写真と文字を同じページに印刷することが可能になったのは1904年のことであり、このため、フォトジャーナリズムと写真が掲載された本や雑誌が最盛期を迎えたのは20世紀に入ってからであった。1912年に明治時代が終焉を迎える頃まで、重大な出来事や時代の流行など、大衆の営みの視覚的描写を担い続けたのは、木版画と素描による空想的な<報道>であった。
これらの発展の影には相互的な関係が存在したと言える。技術的革新と産業構造の変化により、日本における写真の人気と(ゆっくりとした変化ではあったものの)写真資材を輸入に頼らず国産のもので賄う動きが高まる中で、写真そのものは — 家族写真、グループ写真、または記念写真という形で — 凄まじい勢いで前進する技術革新と産業化に対するイデオロギー的な解毒剤のような効果をもたらした。こうして家族アルバムが大衆文化において異常なまでの人気を博した1880年前後は、伝統的な家族の絆が都市化と近代化の波に侵食されつつあることが明らかとなった時期でもあった。また、作業グループや社会的集団など、複数の人々を一つのまとまりとして均質化して写したフォーマルな肖像写真が人気を得たのと同時期に、明治時代後半の日本の指導者たちは、日本の労働者がもっと割のいい仕事が舞い込めばそっちに飛びつき、利己主義と個人主義、ひいては社会主義と無政府主義までが社会機構をズタズタに引きちぎるのではないかという恐れを吐露した。
<記念写真>に切り取られた場面 — 出生から、幼少時代、卒業、就職、余暇、結婚、育児に至るまでの幸福な長旅 — が象徴する人生の立派な功績やそれらが喚起する和やかなイメージが、明治日本の商業写真家によってお決まりのフォーマットとして大衆向けに制作されるようになった時期は、先行きが不透明な時代に人々が悲観と煩悶を抱えていた時期でもあったことを、記念写真とは別の情報源は示唆している。写真屋の男たちは人々の生活を理想化することで生活を営んでいた。写真屋たちは、誰もが居るべき場所を持ち、すべてが上手く運んでいると見る者に信じさせ、彼らの心を和ませるようなスクラップブックを制作し、またそれと同じ要領で、調和を象徴するイメージを手本とすべき姿として世間に広めた。この点において、彼らの仕事はプロパガンダの様相を呈しており、意図的ではなかったにしても、日本古来の<美風>と<調和の取れた>社会的関係を説いた支配階級の美辞麗句と変わらぬメッセージを視覚的に伝えたのである。諸外国で制作されたものと同様、日本の家族アルバムは、写真が物事を記憶にとどめておくため、かつそれを忘れるための手段となる典型例であり、その過程で写真はイデオロギー的な役割を果たしたと言える。
時として、理想化がうまくいかないこともあった。無愛想で現世欲が強いとされていた明治天皇にとってカメラは風流なものだったが、商業写真家が被写体にどんなに派手な服を纏わせ凝った髪型をさせても、その息子で精神が虚弱であった大正天皇の目から濁りを取り去ることはできなかった。理想化が因襲を打ち破ることもあった。1892年に小川一真が撮影した彼の年老いた両親の肖像は、母親が父親の肩に頭をもたせかけている姿を捉えたものだが、当時、男性が断固として支配していた社会において、それは真心と愛情を高らかに表現する驚くべきイメージであった。肖像写真は稀に、皮肉たっぷりで狂気的とも言えるユーモアをたたえた写真も提供した。1893年に江崎礼二が制作した、一見でこぼこの貝塚のように見える1,700人の赤ん坊の顔のコラージュは、その代表的な例である。しかし、明治後期以降、主流の商業写真家たちは肖像写真を通して安定と平穏のイメージを伝え、心の琴線に触れるような希望に満ちた瞬間をとどめることで、小さな神話を創り出していったのである。
歌、小説、画像、政治的表明、歴史的随筆などの創作物がそうであるように、化学薬品とガラス乾板で作り出される写真表現の理想化された世界は、その時代を生きた者たちの現実の一部をも構成していった。それだけでなく、ものを見るための他の優れた方法もそうであるように、写真は自らの神話を否定し、同時にそれを入念に創り上げていった。戦争写真と<カメラの目>というテーマで本コレクションでも紹介しているフォトジャーナリズムの出現と記録写真の成熟に伴い、写真屋の男たちが被写体にお決まりのポーズを取らせて作った世界は勢いを弱めていく。その一方で、美的感覚をより重んじたスタジオ写真家は他分野の写真家と交わることをせず、その結果、極めて独創的な撮影スタイルを生み出していった。この流れは明治時代の終わりに<芸術写真>として台頭し、1930年代には現代的・前衛的ビジョンのまったく新たな高みへと達することとなる。本巻を読み進めていくうちに明らかになるのは、現代の日本人写真家が1940年代以前の10年間を真の<発展の時代>として振り返り、その時代を土台として戦後の日本写真が築かれていったと解釈していることである。
1894〜1895年の日清戦争を機に、日本人写真家は戦争写真の撮影技術を大いに高めていく。日本は戦争を踏み台にして近代国家として浮上したという事実を、カメラが収めた記録を通して知るとき、多くの人の目にそれは凄惨なものとして映るはずだ。しかし、こうしたイメージは当時の人々すべてにそういった印象を与えたわけではなく、また現代人のすべてにとってそうであるとも限らない。日本の写真家が捉えたイメージのいくつかは言葉にならぬ平和への叫びを表出するものであり、他国の写真家たちが残した作品に匹敵するほどの雄弁さで戦争の恐ろしさを語っている。波の立たぬプールに置かれたヘルメットと頭蓋骨や黒焦げの母子が、その代表的な例である。イメージが言葉によってその意味を変えることもある。死とそれに伴う苦痛のイメージが次々と重なっていき、その像が単なる陳腐な写真表現としか見えなくなったとき、見る者の心は麻痺し、目は文字通り、そして比喩的な意味でも霞んでいく。こうしたとき、写真に添えられた説明文が予期せぬ解釈を与え、戦争体験の直接性と特異性へと観者を引き戻し、突如としてその心の目を焼き焦がすのだ。例えば、柳田芙美緒が喉から刀身が突き出た死体を撮った不気味な写真に次のような説明文が添えられていたら、それを見た者の日本の軍国主義に対する印象は変わるかもしれない —「静岡連隊所属の聡明な兵士が訓練中に銃剣自殺」。また、帝国日本時代の戦争写真を目にした現代人が日本とアメリカの行為を並べて考えてみたとしたら、場合によっては聖書に書かれているような解釈に至るかもしれない。日本が海外で犯した殺りくの報いとして日本人が大量虐殺されたという、<自分の行いの結果が自分への仕打ちとして帰ってくる>、<自分でまいた種>というような解釈が成り立つのである。また、アメリカ人が1944〜1945年に撮影された写真記録を目の前にすれば、彼らもまた有罪であったこと、戦争という状況下において無実の者など誰一人としていないということに気づかされるだろう。
しかし、1945年以前の日本において、戦争写真はこのような反戦メッセージを明確に打ち出すものではなかった。その要因として、検閲の問題が複雑に絡んでくる。今ある写真による戦争の記録がどれだけ完全なものかは明確に分かっておらず、そのうちどれだけのものを当時の日本国民が実際に目にしたのかを突き止めることも難しい。1894〜1895年の日清戦争の時代から、戦争写真家の多くは日本軍と直接的な関わりを持つようになり、彼らが撮影する主題は厳しく取り締まられるようになる。現存する中でも特に1931〜1945年に撮られた写真は<不許可>と押印されており、近年になって初めて機密扱いを解除されたものもある。また、1945年の降伏に伴い日本が自国にとって不利となる資料を必死に大量処分した際、他の検閲写真も破壊されたと考えられている。自己検閲が軍による検閲を煽り立て(1940年代初頭の配給制度と全般的な物資不足もこの傾向を助長した)、またその他の理由や背景も手伝って、日本が経験した戦争の多くの側面は、現存の記録には網羅されなかった。例えば、南京大虐殺を記録した日本の写真はたった一枚しかなく、1918年から1922年にかけてのシベリア出兵時の白系ロシア人と白色テロへの日本の関与を取り上げた記録も非常に乏しいものである。柳田が残した聡明な新兵の自殺のイメージを除いて、士官学校の厳しさや徴兵された者たちの絶望や疲弊を伝える日本の写真的記録はほとんど存在しない。プロパガンダは日本兵の大半が「天皇陛下万歳」という言葉を残して死んでいったと言明しているが、生き残った兵士たちは、彼らの仲間が母親を呼びながら死んでいったと告げている。このような真実をカメラが浮き彫りにすることができないのは、それが生きている者の顔と死んだ者の顔は記録しても、生死の狭間にある者の顔を捉えることはないからだ。
戦争の視覚的記録が不完全だったとしても、戦前の日本人が粛然たる思いにかられるような多くの戦争写真に触れる機会を持っていたこと、そして彼らがそれらのイメージに心を打たれたことは明らかである。写真は20世紀に各国が打ち出したプロパガンダにとって不可欠な要素であり、世界に初めて大規模な、そして大々的に撮影された近代戦をもたらしたのは、1904年に宣戦布告なしにロシアを攻撃した、他ならぬ日本であった。1930年代に入ると、ナチスドイツは写真に巧みな操作を施すことでプロパガンダをまったく新たな洗練されたレベルへと進化させ、これに倣った日本の軍国主義者は1937年、内閣情報局と大本営にそれぞれ広報部門を新設する。1940年、最も信頼の置ける日本の写真誌の一つ『フォトタイムス』は、芸術家の国家に対する義務を説いたゲッベルスの言葉を、許可を得た上で引用した。1943年を迎える頃には、写真による国内向けのプロパガンダは狂信的なまでに過激化していく。しかし、このようにあからさまなプロパガンダよりも興味深いのは、戦争写真がプロパガンダになり得る微々たる可能性をもともと本質的に備えているという点である。日本の写真を例に挙げるとすれば、1904〜1905年の日露戦争を記録した写真には、この内なる可能性がはっきりと浮かび上がっている。
各国の写真家がカメラに収めた日露戦争は、写真という観点から見ると非常に見事なものである。ここにある日本人写真家による何枚かの例を見ただけでも、撮影当時にこれらの写真が与えた衝撃の大きさがどれほどのものだったかを想像することができるだろう。20世紀に入ってからも、精巧に作られた木版画は日本の民衆に戦争の様子を伝える主な表現手段であり続けたが、日本において写真が — それが広大な空間を捉えその感覚を見る者に伝える力を備えていたこと、以前使われていた反応の遅いレンズや時間のかかるプロセスでは実現できなかった形で戦争の<真の>側面を映し出す鏡となったこと、さらには時を同じくして起こった新聞・雑誌記事などにおける写真複製技術の飛躍的進歩も手伝って—より説得力のある視覚的手段として真価を発揮したのも、まさにこの時期であった。
日本の兵士たちがしたのと同じように、カメラもまた満州の巨大な空間を、目を見張るような勢いで捉えた。その頃、そしてそれから何十年も後の時代にも、こうした広大な景色の大展望や遥か遠くに見える地平線に、日本人は何か壮大な象徴的意味を見出した。空間を捉えたイメージは、彼らの宿命を暗示したのだ。他国もまた中国国土の分割に尽力していた時代に、人口過密な場所に身を置く力のあり余った者たちが、この満州の広大な新開地が日本にとって軍事的・経済的に欠かせない空間であると考えたのは当然のことだろう。1904〜1905年に撮影された写真が日本人の集団的意識に刻み込んだのは、日本が打倒すべき敵であるロシアとその未開墾の土地、まばらな人口と後進的な人たち、ロシア国家とその君主たちの勢力に打ち勝つ日本の精神といったビジョンであった。山と積み上げられた死体の写真を記録することにより、写真は遂に宿命と使命とを切り離せないものとした。なぜなら、カメラが捉えたそれらのイメージは、アジア大陸への足掛かりを築くという国の本懐を遂げるために死んでいった12万人の日本兵の忘れ得ぬ記念碑となったからである。これほどの大きな犠牲への裏切りが許されるはずはなく、その後の戦争で死体が戦場に積み上げられていけばいくほど、帝国主義を突き進む日本が後戻りすることはできなくなっていった。このような状況下では、愛国心に訴えるむごたらしい写真は、国民を反軍国主義へと効果的に引き込む役目など決して果たせない。それは、国のために死んでいった日本兵たちに負った血の負債を、日本人にしきりと思い出させるイメージに他ならなかったからである。
今の時代を生きる者の目に、こうした戦時中の記録が、それが撮られた時代とは違った意味合いを伝えてくるのは当然のことだろう。延々と広がる地形とそこに佇む小さな人影は、日本の宿命というよりむしろ日本人の愚かさを象徴するかのようだ。現代の観者がまず感じ取るのは、日本が同胞兵士たちに負った血の負債ではなく彼らが宿していた血への欲望であり、囚人の首を切り落とす瞬間にせせら笑いを浮かべて見ている日本兵のイメージは、日露戦争が予示した日本帝国の行く末を非常に的確に象徴している。戦争写真の意味をこのように読み解くとき、そこから高潔さなどはほとんど感じ取れず、それどころか、哀れな日本兵の死体は、軍服のポケットに愛する家族の写真や甘美な女性のピンナップ写真を忍ばせながらも残虐行為に加担した兵士だったかもしれないとさえ思わせる。これらの相反する解釈がなぜ成り立つのかを理解するためには、戦場を日本国内の状況に、戦争写真を日本の内地のカメラが捉えたものに、それぞれ照らし合わせてみなければならない。
戦前の日本においてカメラが写真スタジオの外に持ち出され、意図的な技巧や感傷的な要素などをまったく省いて使われたとき、それが捉えたイメージは海外の戦争写真家が残した記録に酷似していた。ここでの被写体もまた、破滅的な打撃を受けた風景、迫害された人々、対立する者たちなどである。1870年代以降、断頭と死体の公然陳列は外国人のみに限られていたにも関わらず、そこには切断された日本人の頭部を写した写真も含まれている。1944年以前、凄惨な状況は国を繰り返し破壊した自然災害によってもたらされ、被災者の死体はちょうど戦場で倒れた兵士たちのそれのように地面一体に散らばっていた。1923年の関東大震災は10万人を超える死者と行方不明者、50万人以上の負傷者という膨大な数の犠牲者を出した。人々の迫害の主な動機となったのは、人種や国ではなく階級の違いであった。調和と集団への忠誠を謳う支配階級の教戒はきっぱりと否定していたものの、階級差を根拠とした社会的確執は実際に存在し、第一次世界大戦の終焉とともにより確かな動向として組織力を高めていく。カメラはまた、支配層が最も恐れたイデオロギー的な脅威を示唆するような場面も記録している。大逆罪を暗示する写真が、その代表的な例である。こうした内部抗争の記録には、1936年2月26 日のクーデター未遂事件で自国政府に対し武器を取って戦った日本軍の写真すらも含まれている。これら、国内紛争のイメージを頭に浮かべるとき、日本軍による度を越した残虐行為は、混乱、憎悪、激動の舞台を日本国内から国外へと差し替えてしまうような、ある種のグロテスクな効果を帯びてくる。この時代を専門とする学者たちは時に、怒りの矛先の転換、鬱積した怒りの爆発、抑圧の移譲などに言及する。写真はこのような命題を、より感覚的に見る者に伝えるのである。
しかしながら、貧困に喘ぐ自国の社会的風景は、それと相対する風景、つまり日本が20世紀に突入するとともに一層目立つようになった特権層の風景と補い合う関係にあったと言える。ここで学者たちは、逆説、二分法、二元論、不両立などの語彙を用いて抽象的な考えを当てはめようとする。貧困と富が互いに相補うこうした社会的経験を認識・回想する上で、カメラは二つの異なる役割を果たす。まず、写真はいくつもの矛盾を表出する(例えば、迫害された者と迫害する者のイメージを見て、それらの人物が実はどちらの側の人間にもなり得ると気づき、放蕩にふけるコスモポリタンの姿を貧しい農民や労働者と並べたときと、狂信的な軍国主義者と並べたときとでは見え方が違ってくるというような、複雑な食い違いを生む)。次に、写真はこの矛盾そのものを体現する。なぜなら、20世紀における日本の写真の創造的な発展は、中流階級の文化、ブルジョア独自の価値観、コスモポリタンがより幅広い事柄に関心を持つようになったことなど、恵まれた階級を取り巻く様々な状況が、それらすべてが一様に実現したわけではないにしろ、一挙に出現するという時代的背景に根ざすものだったからだ。端的に言えば、この写真の発展そのものが、相対的特権の風景には不可欠な要素だったのである。
戦争に明け暮れ、戦争によって破壊された日本の記憶は忘れがたいほど鮮明であり、マッチ箱のような小さな家がひしめく町や土にまみれた貧しい農民たちは実に圧倒的なイメージであるため、第二次世界大戦前の欧米諸国の発展に多くの点で匹敵するような政治的・文化的発展を戦前の日本が遂げたことを、我々は忘れてしまいがちだ。概ね大正天皇の治世(1912〜1926年)に起こったため<大正デモクラシー>と大まかに定義されたこの時代は、事実上、世紀の変わり目から1930年代の始めまで続いた。ドイツのヴァイマル共和政期における政治や芸術と幾分かの類似点を持っていた大正時代は、〔それに続く1930年代に日本が実際に辿った歴史とは〕違う未来を想像させるような曖昧なイメージを生み出す時代なのだ。
大正デモクラシー時代の経済的土台は、ダイナミックであると同時に不安定なものだった。これは、日露戦争と第一次世界大戦に刺激され、多数の中小企業の台頭、都市部の労働者数の増加、これ見よがしのにわか成り金の出現、巨大財閥の隆盛などが次々と起こったためである。政治世界においては、選挙政治が精力的に推し進められる一方で、急進的な左翼活動も盛んであった。文学の世界では、自然主義、ロマン主義、観念主義、人文主義、耽美主義などの学派を意識的に支持する風潮が見られ、絵画の分野では、日本と西洋の様式がともに花開く。アーネスト・フェノロサと岡倉天心が熱心に唱えた<オリエンタリズム>は1880年代に明治の国粋主義と融合し、極めて理想主義的な日本の伝統的芸術様式を復活させた。西洋画は、1890年代に日本に渡ってきた印象派や1910年代に流行したフォーヴィスム(野獣派)やキュビスムなどの後期印象主義により、新しい命を吹き込まれた。映画と近代劇は1900年代前半に姿を現し、1920年代に入ると、エログロナンセンスの流行に乗ってキャバレーやフラッパーといったけばけばしい文化が日本に輸入され、モガやモボ(モダン・ガール、モダン・ボーイという言葉を不自然に縮めた呼び名)はこれを取り入れた。
こうした環境の中、日本の写真はいくつかの違う方向へと発展していく。例えば、広告やプロパガンダの分野へと手を広げた商業写真家は、その当初、石鹸や化粧品を手にし、尽きることなくビールを注ぎ続ける着物の美女たちの姿ばかりを撮影した。着物姿ではない若い女性がきらめく赤ワインのグラス越しにこちらを見つめる温かみを帯びたセピア色のポスターに代表されるような控えめで穏やかな売り込み手法は、1922年に絶頂期を迎える。若干18歳の女優が<美味・滋養>を謳った赤玉ポートワインを勧めるイメージは当時センセーションを巻き起こし、今日に至っても戦前日本で制作された商業芸術の中で最も有名な作品であり続けている。
一部の写真家が見る者を商業的に誘惑する技を磨いている間に、多くの写真家は芸術の世界に魅せられていく。西洋がそうであったように、写真を芸術として認識する動きが写真を新しい方向へと導き、その初期段階で<芸術写真>は美術作品をつぶさに模倣した。この流れを勢いづけたのは、写真産業や鹿島清兵衛を始めとする進取の気性に富んだ写真のプロたちが後押ししたアマチュア写真家であった。鹿島が明治後期に巧みに捉えた外套を纏った男たちの姿は、スタジオ人物写真のジャンルと新生の耽美主義とを繋ぐ懸け橋となった。その一方で、彼の華々しい活動は、アマチュアが活躍する時代を導いた旺盛な企業家精神を体現している。明治時代の終盤に鹿島が企画した撮影旅行には何百人もの上流階級の人々が参加したが、彼らは芸者や音楽隊などをお供に貸し電車で山間を走り抜け、飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをしながら、気が向いたときだけ写真を撮ったと言われている。
写真の人気が高まるにつれ、同好会、展覧会、出版物、教育課程などが活況を見せるようになり、写真の機材や資材の国内生産も増加していく。1889年には日本で最初の写真協会が設立され、商業写真家とアマチュア写真家の両方が会員となった。1900年には、最初のアマチュア向け技術マニュアルが出版される。ゆふつヾ社が結成され、加藤精一が画期的なエッセイ「芸術写真について」を出版した1904年、<芸術写真>という呼称が高らかに叫ばれるようになり、1907年には写真展覧会の企画が頻繁に行われるようになる。そして、若者を対象とした最初の写真同好会が1913年に組織される。
1890年代には既に何冊かの写真誌が出版されており、その一つ『写真月報』は1893年から1940年まで発行された。1921年になると、専門誌が雨後の筍のように次々と制作され、その中のいくつかは写真分野の主要誌として生き残った。中でも特に人気を集めたのは、第二次世界大戦中の休刊を除いて1921年から1956年まで出版された『カメラ』、1924年から1941年まで出版された『フォトタイムス』、1926年から1941年まで出版された『アサヒカメラ』であった。1922年に創刊され、シンプルに『アマチュア』というタイトルを冠した雑誌は、その翌年の関東大震災により閉刊に追い込まれるまでに出された全号が各1万部もの売り上げを記録したと言われている。1920年代には、多くの写真を掲載した週刊・月刊誌が大量部数発行され、その時期に台頭し始めた主要な新聞社は、フォトジャーナリズムの奨励だけでなく、写真集の出版や写真展への出資などにも貢献した。また、アルス(ラテン語で<芸術>を意味する)などの出版社もこの時代に設立され、芸術写真を擁護した。
第一次世界大戦がもたらした好景気は、日本の写真を様々な角度から刺激した。アマチュア写真家が急増し、1916年から1922年の間に写真資材の輸入額は8倍にも膨れ上がる。これと同時にカメラワークに対するプロ意識が目に見えて高まると、日本の写真産業はカメラ、フィルム、乾板、印画紙など、撮影に必要な器具や材料の自給を目指し、それまで以上の飛躍的な進歩を遂げる。1900年には写真の教育課程が設けられた。東京美術学校において1915年から1926年までカリキュラムに組み込まれていた写真は、その後、東京高等工業学校に移管された。1923年、正式認可を受けた小西写真専門学校〔その後、東京写真専門学校に改称〕が小西本店の後押しを得て設立され、丸3年に及ぶ写真課程を提供するようになる。外国製のカメラには裕福なアマチュア写真家だけでなくプロの写真家も惚れ込み、コダックの小型軽量カメラ、ヴェスト・ポケット・コダックの輸入が1915年頃に始まるまで、彼らは英国製のカメラを特に好んで使用した。1920年代半ばにライカが登場するまで、コダックの人気は継続する。しかし、世紀の変わり目から、小西の率いる複数の製造業者が国産モデルのカメラを切れ目なく生産するようになる。これらの製品につけられた名前は、チャンピオン、パリ、ノーブル、パール、アイデア、リリー、ミニマムアイデアカメラ、アイデアフレックスなど、英国風のものばかりであった。ある評論家は、戦前の日本製カメラの名称は1945年以降に販売された日本製たばこの銘柄のようだと指摘している。
ピーター・ヘンリー・エマーソンが提唱した革新的な写真理論と写真作品が1880年代後半に初めて登場した西洋に比べ、日本における芸術写真の発展は少し後れを取っていたと言える。写真を芸術として(高い寓話性を帯びたヘンリー・ピーチ・ロビンソン風の作品とは対照的に)紹介する草分け的な展覧会が、1891年から1893年にかけてヨーロッパで開催された。アメリカでは、1890年にドイツから帰郷したアルフレッド・スティーグリッツが1902年にフォト・セセッション(写真分離派)という名の写真グループを結成し、著名な写真家仲間たちとともに1902 年から1917年にかけて機関誌『カメラ・ワーク』を出版する。一方、上述の如く、日本の写真が芸術表現として人の目に触れるようになったのは1904年頃のことで、西洋が打ち立てた先例があってこそ日本の写真技術は前進し、写真にまつわる思想にも新たな息吹が吹き込まれたのである。1904年から1909年にかけて、秋山轍輔はゴム印画法やその他の<ピグメント印画法>を取り入れた。写真の表面に普通の写真とは違う素描のような印象を持たせるため、秋山はきめの粗い印画紙を用い、ソフトフォーカスの使用やイメージの変形、大胆な抽象化などにより芸術的な効果を模索した。こうして日本が西洋の傾向を取り入れていたことは紛れもない事実だが、日本人の芸術写真愛好者たちは、単に海外の流行りを真似ていたわけではない。
誰が誰を<影響>したかという疑問の答えを見つけることは難しく、20世紀初頭に日本人写真家が西洋の写真を目にするに至った経緯もはっきりとは分かっていない。エマーソンは早い時期から日本の写真家の間で知られており、ロンドンで開催された写真展は1892年の時点ですでに日本にも巡回していた。アルヴィン・ラングダン・コバーンがカメラを通して見出した抽象的なパターンが高く評価される中、日本人はとりわけ、今日の西洋写真史において度外視されているE・O・ホッペの著作物と写真作品に感銘を受けた。野島耕三の写真家としての目は明らかにポール・ゴーギャンの絵画を捉えており、芸術性を求めた日本の写真作品の多くはヨーロッパの印象派画家たちを魅了したに違いない。しかし、印象派の画家たちがまず初めに触発されたのは、日本から彼らの住む欧州諸国に届いた陶磁器を包(くる)んでいた伝統的な版画作品のほうであった。このように、一体どちらがどちらに影響を与えたのかという問いは複雑さを孕んでおり、その答えを見つけることは不可能に近いのである。
日本の写真家が芸術家としての自負を持ち始めた当初、日本社会の大部分がアーネスト・フェノロサと岡倉天心、そして国体を信奉していたという事実が、誰が誰に影響を与えたのかという疑問をさらに複雑化する。写真家は突如として、水墨画の伝統が持つ卓越したキアロスクーロを見出し、これを再現した。ここまで直接的でない例としては、古典的な様式で知られる横山大観など、同時代の名画家を敬服し、彼らの絵画を真似る写真家もいた。さらに間接的な例で言えば、日本の写真家たちは、もののあわれが僅か17音節の中に凝縮される俳句という母国の伝統文学を通して印象派に辿り着いた。俳句ほど印象主義的な—もしくは絵画的な—ものは、他に存在しない。カメラのフィルムに俳句精神を現出させた最も著名な日本人写真家の一人は福原信三であり、彼は仲間の写真家たちに俳句風の助言をしたことでも知られている(「生涯の全歴史を一つの石の中に、人生における複雑な関係を一本の木の中に、命の内なる活動を一枚の葉の中に見出しなさい」)。1920年代半ばに差しかかる頃、福原は日本の写真芸術が優れた木版画にも引けを取らぬほどの独特な<国民性>を反映するようになったことを実感する。それと同時に、フランスで写真を学ぶ機会のあった福原は、印象派のスタイルを自作に取り入れている。理論的には容易でなくても、実践の面においては、日本固有の精神と国際的なアイデンティティの両方に同時に到達することは可能であった。
1920年代に入る頃、芸術写真を目指していた日本人写真家の間では、自分たちが国際的な写真の舞台で一目置かれる存在になりつつあるという期待が生まれていた。写真専門の刊行物は、英語の説明書きや前書きを掲載して外国人読者を引き込もうとした。また、1927年にスタートした国際写真サロンの記念すべき第一回目が日本主催により東京で開催されたことで、国際化時代への期待に拍車がかかる。これに伴い、海外の写真展への日本人作品の出展を求める声も高まっていく。ある日本の写真誌を宣伝する名目で1928年に英語で出版された広告は、この時の興奮を次のように伝えている。
「日本にあるのは、お馴染みの桜見物と色付きの木版画だけではない!日本にあるのはピクトリアル写真に他ならない。ここ数年の間に、日本の写真芸術は花開いただけでなく、その甘い香りと美しい光を世界中に放ったのである。
今日、世界中のカメラマンや写真愛好家の誰もが、日本における写真の発展を心に留めずにはいられないのだ。」
実際、日本の写真はそれに続く10年間に目覚しい成長を遂げるが、この<絵画のような写真>への甘ったるい賛辞が示すのとは違ういくつかの方向へと発展していった。芸術写真の分野は本巻でも紹介しているような洗練された作品を生み出すこともあったが、全体としては霞の立ち込める場面や不鮮明に描かれた人物ばかりが登場するジャンルとして分類されてしまう。1928年に開催された大規模な展覧会について、ある評論家は、日本人写真家は日常生活よりも自然を好み、自然の中にある動よりも静を好むと批評している。おしなべて、彼らは創造性に乏しく、人間性に無関心で、難解で高尚なものを好んだ。こうした危機感に同調した多くの日本人写真家は、1920年代半ばを迎える頃には、芸術写真は単なる技巧と化し、オリジナリティのない写真屋たちの小ぎれいで型にはまった肖像写真と変わらぬほど感傷的で非現実的な理想像に成り果てたと感じ始める。
芸術写真の衰退と<大正デモクラシー>の終焉が同時期に起こったことの裏には、歴史学者にとっては非常に興味深い意外な展開があった。<大正デモクラシー>の終焉は、日本の写真が急速に多様化し、刷新的な成長を遂げた10年間の始まりとも時を同じくしたのである。現代の目には、これは思いがけないことのように映るかもしれない。なぜなら、それは軍国主義と自由の抑圧が高まりを見せた<幽谷>の時代に、写真がかつてないほどの繁栄を見せたということになるからである。1930年代を通して続いたこの<発展の時代>を国家が本格的に弾圧するようになったのは、1940年頃のことであった。
より詳細な分析によってはっきりと見えてくるのは、これは後から振り返るからこそ得られる知見でもあるのだが、上記の事実は文化的・社会的な不毛の地に気まぐれで起きた特異な繁栄などではなかったということだ。日本社会における様々な領域は1930年代に凄まじい変貌を遂げた。芸術と科学のいくつかの分野は<大正デモクラシー>時代に動き出した発展の勢いを1930年代まで持続し、1920年代に生まれたロジックを実践し続けた。他の分野では、政治的・道徳的な面でこの時代が呈していた過酷な様相が、写真の創造性を駆り立てることとなる。例えば、戦前の日本で撮影された最も素晴らしい — <人間主義的>ですらある — 記録写真の一部は、1930年代に新傀儡帝国・満州国で撮影されたものであり、それより半世紀も前に北海道の新開地が日本写真の世界で果たした役割を想起させる。
この<発展の時代>における写真は、複数の違ったスタイルや呼び名—新興写真、報道写真、前衛写真、リアルフォト、超現実的写真 — を採用し、国内で不安定ながらも推し進められつつあった資本主義の影響と圧力に、西洋諸国からの圧倒的な影響がぴったりと噛み合っていく様を反映した。西洋の影響で最も分かりやすい例は、ライカの登場と、それによってもたらされた35mmフィルムによる撮影である。写真誌『月刊ライカ』が1934年に創刊され、日本で最も評価された写真家の一人・木村伊兵衛が1938年に『Japan through a Leica』(英語の原題)を出版したことは、納得のいくタイミングだったと言えよう。
1920年代後半に入ってすぐ、日本人は絶え間なく普及されるようになった記事、翻訳、展覧会、体系立てて制作された写真の複製品(国際写真の年鑑を含む)などを通して、西洋における写真の最新動向にほぼ制限なしにアクセスできるようになる。彼らは特に、ライカが生まれた国で展開していた前衛的な流れ—新即物主義(Neue Sachlichkeit)—と、モホリ=ナジ・ラースローなどの革新者が表明し、1926年頃日本に初めて持ち込まれたバウハウスのビジョンに共感を示した。
ナチスが掌握したドイツに日本人写真家が強い関心を持ったことは、バウハウスが提唱した芸術と技術の新たなる統合を思い起こすとき、深い意味合いを帯びてくる。なぜなら、ドイツのこうした芸術理論に対して彼らが見せた感受性は、母国・日本も今や近代性への課題とその誘惑—少なくとも(ここには矛盾があることを忘れてはならないが)近代的様式への関心—に直面しているという事実に端を発していたからである。戦争景気(並びにその破綻)、技術とコミュニケーションの急発展に加えて、第一次世界大戦後の日本では、建造技術、都市化、産業化、消費者主義など、枚挙にいとまがないほど多くの<ブーム>が起こった。1923年の関東大震災によって全壊した国の最大都市は、より近代的な設計で再建される。そして、1931年に突入した愚鈍で独り善がりの帝国主義の時代は、重・化学工業に<第二の産業革命>をもたらすきっかけとなる。不均衡な資本主義と二番手の帝国主義に苛まれていた日本がもう一つ、かつてないほどに突きつけられたのは、整然と立ち並ぶ近代的な建築物や手入れの行き届いた高性能な機械であった。このような状況における美的・心理的・政治的・象徴的な選択肢は幅広く、日本人写真家はその多くを掘り下げていった。
それらの選択肢は必ずしも前衛的なものではなかったが、個々のスタイルに違いはあれど、1930年代前半の主要な写真家は皆、<新興写真>の創造を目指すという明確な意識を共有していた。世に広まったこのフレーズは、1930年に創設された協会と雑誌の名前にも採用されたが(新興写真研究会と、その会誌『新興写真研究』)、これは写真史家にとってしっくりくる呼び名だっただけでなく、社会史家と政治史家の興味をも駆り立てる言葉であった。新興写真の内含する語彙は、革新派の(また、イデオロギー的に柔軟性のある)理想と1930年代に日本中に言い広められた次のような呼称とに、ぴったり合致していた—<新俳句>、<新官僚>、<新財閥>、究極的には国内の<新体制>と国外の<新秩序>。さらには、新しいものを追い求める流れの中で、これらの写真家の多くは<旧>式の芸術写真からの脱却を明確に実行した。因襲を打破する彼らのこうした姿勢は、1932年に伊奈信男が論文「写真に帰れ」の中で主張し、しばしば引き合いに出される<リアルフォト>擁護の立場に立ったマニフェストの文言に示唆されている。
<芸術写真>と絶縁せよ。既成<芸術>のあらゆる概念を破棄せよ。偶像を破壊し去れ! そして写真の独自の<機械性>を鋭く認識せよ! 新しい芸術としての写真の美学 — 写真芸術学は、この二つの前提の上に樹立されなければならない。
新興写真について語った文章のほとんどがそうであったように、伊奈のこの宣言はいささか曖昧である。しかし、このような言語的な曖昧さは、創造性に富んだ多様な写真的試みを促した。芸術写真がその様式を絵画に、その趣を甘く空想的な主観性に見出したのに対し、前衛的な<新興写真>は近代的で機械的な世界を手本とし、<現実>、<事実>、非個性を重んじる感情に流されない客観性を好んだ。この新しい写真は建築物と機械、コンクリートと鉄で造られた近代世界に焦点を合わせ、無秩序でめまぐるしい変化そのものをフォルム、秩序、一貫性へと変換し、写真の中に現出させた。この試みが果たして本当に客観的で感情に流されないものであったかは別問題である。
その一方で、現代社会における物質的なフォルムを、不満感や批判とも取れる感情を込めて表現することも可能だった。このスタンスを体現する好例は、言論の場となった有名誌『中央公論』に1931年に掲載された堀野正雄の数枚のフォトモンタージュ作品《大東京の性格》である。フォトモンタージュは革新的な欧州作家を魅了したもう一つの技術であり、堀野は自作のデザインがモホリ=ナジの作品からヒントを得たものだと認めている。ダイナミックに配置・構成されたモンタージュ、あるいは複数枚置かれた写真、もしくは合成写真は、連携と不均衡の両方を図式的・弁証的に同時に伝えることができる。堀野が複数のイメージを組み合わせ、並置し、交差させてできた情景から立ち現れた近代的な東京の姿は過酷で不安定なものであった。しかしその翌年、堀野は写真集『カメラ・眼×鉄・構成』の中で、近代の船舶を撮影した有名な写真シリーズを発表する。当シリーズは、いわゆる機能的美学に特徴的な近代的フォルムを、実は彼が単純に心酔していたことを伺わせる。
伊奈信男のマニフェストが明示するように、<機構>を重視するこうした流れは写真家たちに、機械は彼らの周りにあるだけでなく彼らの手の中にもあるのだと認識させた。カメラもまた機械的装置であり — 絵筆ではなく、単なる鏡でもなく、人間の目でもない — その<機械性>を利用することで、現実を独自の感覚で捉えることが可能になったのである。現代の観者にとっては当たり前に思えるかもしれないが、その時代の写真家たちにとってこれは大きな発見であり、真にものの見方を変える発見だった。複数回の露出、シャッタースピードの調整、レンズの操作など、さまざまな技術を駆使して、写真家は外界に存在する種々のユニークな印象をカメラの中へと取り込むことができるようになった。現代人のものの見方を形成する上でさらに意義深かったのは、写真家がカメラの可能性をフル活用してクローズアップや型破りなアングルを多用し、被写体の一部のみを切り離したり思いがけない視点からそれを捉えることによって、感覚の新世界を見出したことである。的確な視点から細部にわたって<現実を捉える>能力をそもそも買われていたカメラは今や、イメージを断片化し従来の視点を超越することで、被写体の織りなすパターンや形象とその空間との関係性を新たな切り口で表現する機構として評価されるようになった。
写真家たちがクローズアップを多用し、カメラの機械性を様々な新しい形で活用していくにつれ、機能的近代性の崇拝には欠かせないモチーフであったくっきりとした直線は、柔らかな線へと変わっていった。何が<リアル>なのかを見極めるのはますます困難になっていく。理性は不確実に取って代わられ、事実は示唆に取って代わられる。このように、新興写真が呈したもう一つの様相は、芸術写真が試みられた時期にすでに顕著であった半抽象的、あるいは抽象的な構図の推進であり、この傾向は新興写真によってさらなる進展を見せた。この流れにおいて、写真家の新たな客観性が生み出したのは、非客観的なイメージであった。また、それとは違う方向に向かう写真家もいた。前衛的な写真家は、人間的要素や夢と非現実の要素を取り入れることで、物質主義的な現実性から脱却しようと試みた。彼らのばかばかしいほどに理性的な写真作品は、1920年代のヨーロッパに登場した近代的芸術運動・シュルレアリスムにヒントを得たものだ。これらの写真の多くがクローズアップと抽象、あるいは抽象と超現実の境界を曖昧にするものであったことは言わずもがなである。日本人写真家はまた、カメラを使わない<レンズなしの写真>であるフォトグラムや、マン・レイが開発したソラリゼーションなど、西洋の技術を次々に採用した。
機械を称賛する者たちが完全に排除し、超現実主義者がばらばらに切断した上で提示してみせたこと、つまり人間を、新興写真を進歩させた他の写真家たちは分解されていない全体像として、そして畏敬の念すらたたえて表現しようとした。機械や近代世界の形状からのこうした離脱もまた<リアル>の名の下に遂げることが可能であり、1930年代の前衛写真は人間という被写体の印象をそれまでよりも高度な技術で様々な角度から捉えている。19世紀半ばに写真がもたらされてからずっとそうであったように、有名人と無名な者の両方が撮影の対象となった。今やフィルムが使用されるようになった人物撮影には、ソフトフォーカスやスナップショットといった手法が使われ、人々は独特なアングルや以前よりも<自然な>ポーズで撮影された。芸術写真と新興写真の懸け橋となった作品を生み出した野島耕三は、女性とヌードのジャンルにおいて最も独創的で優れた習作の多くを1930年代初期に制作した。この時、野島はすでに40代であった。1901年に生まれた木村伊兵衛は、肖像写真とストリートスナップの達人として1930年代に突如現れた。渡辺義雄が技巧に走ることを意図的に避け、ミュージカル・レビューの楽屋を取り巻く喧騒と混乱を捉えたのに対し、濱谷浩は地方の習俗にゆったりとした優しく中立的な眼差しを向けた。この時期の最も優れたアマチュア写真家・安井仲治は芸術写真の絵画的な様式を捨て、1942年に若干39歳〔正しくは38歳〕でこの世を去るまで、力強い社会派リアリズム作品を制作した。多才な堀野正雄は、フォトモンタージュ作品と鋼鉄で造られた世界を捉えたイメージで評価を確立する一方で、労働者階級の人々にもカメラを向けた。
1930年代半ばの日本にアメリカのロイ・ストライカーや農業安定局に比肩するような人物や組織が存在していたら、こうした無力な貧困層を描出した作品は、真に総体的なドキュメンタリー像となり得たことだろう。しかし、広範囲に及ぶドキュメンタリー表現と呼べるものは日本本土の外で作られたもので、それは帝国主義者の理想を強く反映するものであった。つまり、これは中国東部の主要三地域を拠点とする日本人写真家の作品であり、1930年代に出版された写真大観の題名にもなった、いわゆる<新満州国>における新興写真であった。30年前にロシアとの戦時下で記録された写真と同様、満州で撮られた写真はどれも、空間、苦境、宿命といったものを力強く表出するもので、決して新国家の人々を見下すようなイメージではなかった。最も知られる日本人カメラマンの多くが1930年代を通して満州国を訪れたが、その時期に撮られた写真の中で特に優れているのは、その地に定住したアマチュアとプロの写真家によるものである。彼らが日本政府、満州を統制していた関東軍、さらには南満州鉄道からの後押しを得たこと、生涯を写真に捧げた淵上白陽が彼らの実質的なリーダーとなったこと、満州を拠点に何冊かの写真誌を出版し、新植民地に自らの写真作品を流布することができたこと、そして東亜新秩序の極めて理想主義的な夢を信奉しているようであったことなどがその理由として挙げられる。
1930年代に人間のありようを撮った写真家は、フォトジャーナリズム、日常生活の絵画的な記録を目的の一つとするジャンルとして再定義された<報道写真>、プロレタリアの芸術運動など、複数の動向と関わりを持つ様々な流派に感化された。ここでさらに言えるのは、これらの写真家が肖像写真に対して以前に劣らぬほどの興味を抱き続けただけでなく、芸術写真の隆盛の時代に生まれ今や少なくとも表向きには時代遅れとされながらも、西洋から導入された理論や事例によって蘇った美的感覚を、明らかに取り入れていたということである。1930年代半ば以降に彼らが殊に影響を受けたのは、ドイツで小型カメラによる写真を実践し、彼らと同じく伝統的な写真美学を評価し続けたパウル・ヴォルフの教えと写真作品である。1935年に日本で開催され多くの来場者を記録した二度にわたるヴォルフの写真展は、「これこそ新時代の芸術写真であり、古き<芸術写真>と新しき<新興写真>は両者の果たすべき使命を大方全うしたと言えるであろう」という非常に意義深い称賛を得た。
こうした新しい動向から生まれた写真の一部は戦争写真と<カメラの目>というテーマでここに前述した写真へと徐々に変化し、その一方で、まずは会社のため、次いでは国家のために作られたあからさまなプロパガンダへと変化していくものもあった。<真実>や<現実>の新解釈という名の下に厳かに進歩を遂げた近代写真の構想と技術は、石鹸などの商品を売るという目的にも簡単に適応することが可能であり、消費財の大げさな宣伝のほんの一歩先にあったのは、日本国、拡大する帝国、そしてついには戦争そのものの宣伝であった。最も有名な写真家の多くは広告やプロパガンダ作品を手がけるようになるが、彼らは常に二種類の観客、つまり日本人と外国人を念頭に置いていた。
西洋の影響は、ここでも色濃く見られる。1928年にはすでに、その時代の商業美術に関する複数巻本のうちの一冊がヨーロッパの広告に充てられており、広告美術やその他の芸術分野へのバウハウスの影響は周知の事実である。しかしながら、日本における広告写真が本格的に前進したのは1930年のことであり、これは日本最初の広告写真家協会が設立され、日本人写真家が東京で開催された第一回目の国際広告写真展の一等と三等に輝いた年であった。その翌年、木村伊兵衛を軸とする写真家チームは<純粋度99.4%>の花王石鹸の広告にスラム街の写真を起用し、従来のソフトな売り口上からの劇的な脱却を図る。この写真の実に印象的な構図は、複数の点で新生面を開いたと言える。それは、記録写真の分野で最も伸びを見せていた傾向のいくつかを宣伝屋の領域へともたらしたこと、大衆向けに作られた広告であったこと、非常に長い文章が組み込まれたこと、そして、日刊紙の一面広告として大きく掲載されたことである。
これらの動向は新たな国内市場と新手の商業的プロ意識を示唆するが、これは時期を考えると予想外の展開だったと言えるだろう。1931年は満州事変の年であり、経済指数を見る限り、日本はまだ世界大恐慌のどん底にいた。しかし、フリーランスの写真家と新設の写真課程の卒業生たちが様々なデザイナー、ジャーナリスト、広告製作者らと提携し、大衆に高級品を売り込んだり、露骨に<モダン・ガール>の需要に応えたのはこの時期だった。1930年代には、革新を意味する言葉が広く浸透した時代にふさわしい『新興婦人』というタイトルの女性向け雑誌も出版され、また1937年には余暇を楽しむ新興の女性たちの一部が<レディス・カメラ・クラブ>という英語のグループ名を冠した写真同好会を結成する。これと同時期に、完成度の高い広告キャンペーンが英語圏の市場に向けて実施された。1928年の時点で自国で花開いた芸術写真を西洋に輸出することを夢見ていた日本人は、1930年代半ばを迎える頃には西洋人に自動車、テキスタイル、電球、マンダリンオレンジなどを売るために、洗練された写真を撮影するまでになったのである。
1933年より商業写真の拠点となった日本工房(1939年、国際報道工芸株式会社に改組)は、ナチス政権の樹立前にドイツで写真を学び、同地でフォトジャーナリストとしても活躍した名取洋之助が中心となって設立された。外国人向けの商業広告の大部分を請け負った日本工房は、1934年には日本という国そのものを西洋に売り込む事業へと乗り出す。この対外宣伝という目標を達成するための手段として選ばれたのは、英語で書かれたグラフ誌『ニッポン』であった。それより一年先んじて、満州国において同じくバイリンガルの雑誌『満州グラフ』が創刊された(創刊時には<ピクトリアル・マンチュリア>、後に<マンチュリア・グラフ>と英語の副題がつけられた)。盧溝橋事件と宣戦布告なき対中<殲滅戦争>の勃発から間もない1938年、名取の率いる写真家チームは英語のグラフィック誌『シャンハイ』の出版を開始し、その翌年、さらに『コーマス・ジャパン』、『マンチュコ』、『カントン』の三誌を創刊する。続く1939年、ジャパン・フォトサービスは『ギャールズ・オブ・ジャパン』と題された書籍を戦場に送り、西洋人の目を楽しませた。その後、『ヴァン(Van)』(1940年創刊)や『フロント(Front)』(1942年創刊)などのグラフ誌がヨーロッパと東南アジアの読者に向けて制作された。
日本工房を始めとする組織に携わっていた写真家たちは、自ら撮影した写真を対外的に売り込む過程で、<近代的>、<前衛的>スタイルを保守的な用途に取り入れるようになる。例えば、モンタージュ、あるいは合成写真は、かつて有していた緊張感や矛盾といった要素を捨て、統治側の教義を強化するための純然たるプロパガンダを広める手段となった。1934年に日本工房が制作した先端的なプレゼンテーションはフォトモンタージュの形を取り、秩序、発展、日本の洗練された嗜好などのイメージを鮮明に華々しく描いている。その4年後、シカゴで開催された国際見本市に日本人が出品した高さ約180センチ、幅約420センチの合成写真は、新たなスタイルの試みである。木村伊兵衛と小石清による写真を原弘が構成したこの見事な写真壁画には、20世紀を通じて親日家の心をくすぐったお決まりのイメージのすべてが盛り込まれている。桜の花、富士山、袖を引きずった芸者、静寂を重んじる文化の典型的なシンボル(鳥居、仏塔、鎌倉の大仏)、古城、国会議事堂、数棟の近代的な大建造物、そして近代的な船が一堂に会した。1943年までに、国家のためのこうしたカメラワークは手に負えぬほどの急増を見せる。熱狂的な兵士たちと踏みつけられたアメリカ国旗を描いた有名なポスターは金丸重嶺の写真を組み合わせて作られたもので、東京都心の日劇ミュージックホールの前面を覆い尽くす約170平方メートルの巨大ビルボードとして初披露された。技術を駆使したこの力作は後に幾度となく複製され、そこには古典から借り出された一つの古めかしいスローガンが説明書きとして添えられた—「撃ちてし止まむ」。概して、果ての果てまで戦いぬけ、という意である。
しかし日本の果ては、1943年にミュージックホールの前に立っていた誰にも想像し得なかったほど早く訪れ、それは彼らが思うよりもずっと苦く、恐ろしいものであった。そしてカメラは、芸術性や技巧などを駆使することなく、その惨状を記録したのである。
